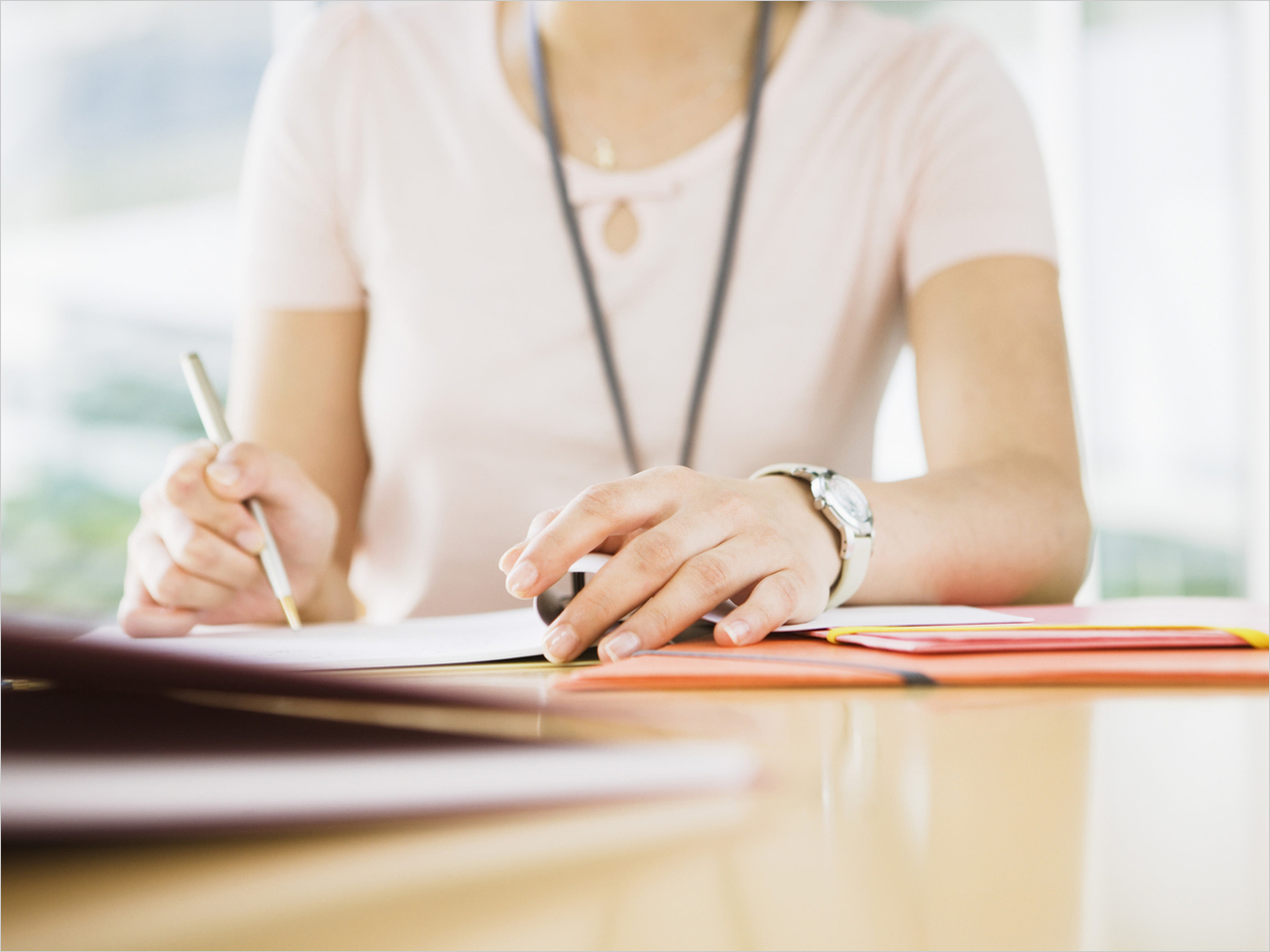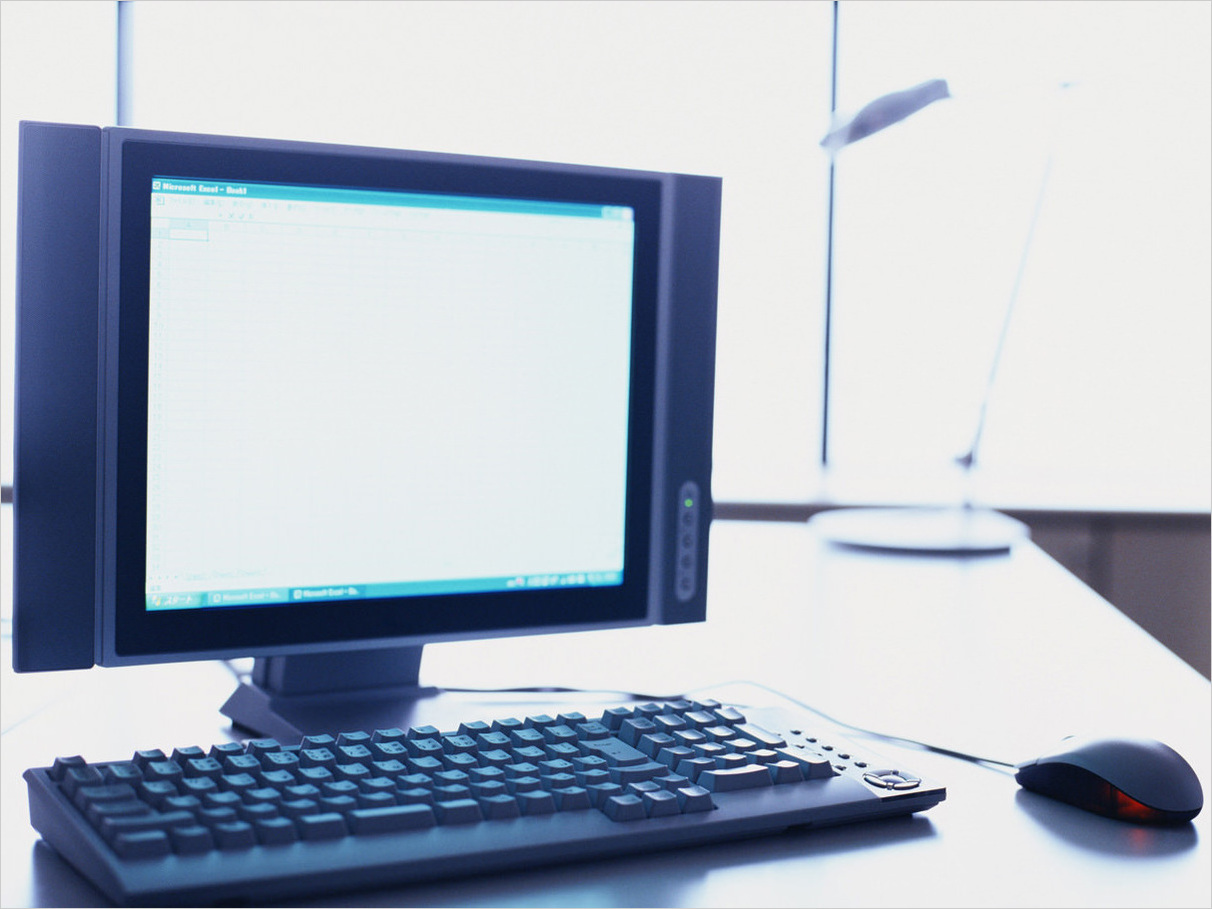働き方改革関連法が2019年より順次施行されます。その中でも2019年4月から施行されるもので主なものについて簡単に記載します。
1.労働基準法に時間外労働の上限規制が導入(中小企業は2020年4月施行)
原則1週間40時間、1日8時間を超えて労働できる時間外労働時間の限度は、原則1月45時間かつ1年360時間となります。ただし、以下のような特例があります。
・臨時的な特別な事情がある場合として、労使協定を結ぶ場合の限度時間は1年720時間とする。
・休日労働を含み2か月ないし6か月の平均が80時間以内とする
・休日労働を含み1か月で100時間未満とする
・1か月45時間の時間外労働を上回る回数は、1年で6回までとする
上記規制は以下の業種については適用が5年後に猶予されます。
・自動車運転の業務、建設事業、医師、鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業
また、具体的な上限時間については特例や検討事項もあり、今後変更される可能性もあります。
そして、新技術・新商品等の研究開発業務については、医師の面接指導、代替休暇の付与等の健康確保措置を設けた上で、時間外労働の上限規制は適用しません。
2.年次有給休暇の年5日取得の義務化
事業主は、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、毎年5日、時季を指定して有給休暇をを与えなければいけません。ただし、労働者から時季を指定した場合や、計画的付与であらかじめ定められた有給休暇の日に取得している場合は、それらの日を除いた日数が5日に満たない場合に不足分を与えなければいけません。
例)年休基準日 平成31年10月1日
時季指定した日 平成31年11月1日、平成32年2月1日
計画的付与日 平成32年8月16日、8月17日
この場合は平成32年9月30日までに1日を労働者の意見を聞いて付与しなければいけない。
施行日(平成31年4月1日)以降に有給休暇の基準日がある場合は、施行日以降初めての基準日から新法が適用されますので、それまでの期間は従前の通り5日の付与義務はありません。
また、有給休暇を管理する帳簿を作成しなければならなくなりますので、事務的にたいへんですが、無料でダウンロードできるソフトもあるのでうまく活用していきましょう。
3.フレックスタイム制の見直し
フレックスタイム制の清算期間の上限が、1か月から3カ月に変わります。ただし、1か月を超える清算期間を定めるフレックスタイム制の場合は、労使協定に定めて監督署へ届出する義務が生じます。また、1か月ごとの各期間を平均して1週間当たりの労働時間は50時間を超えない範囲にしなければいけません。
4.労働時間の把握の義務化
労働時間の把握については、管理監督者も含むすべての労働者について、客観的な方法その他適切な方法により行わなければいけません。具体的な方法については今後通達で定められるようです。
5.長時間労働の医師面接指導の変更
現行では、1か月の時間外労働が100時間を超えている労働者からの申し出がある場合、医師による面接指導を実施しなければいけませんが、新法では100時間が80時間に変更します。1か月の時間外労働が80時間を超えるかどうか、前記4でも記載した通り、労働時間を客観的な方法等で把握して、超えるようであれば労働者に意思確認をして、できるだけ面接つなげるよう心がけてください。
上記のものが主な改正点ですが、この改正に伴って就業規則や時間外協定の変更が必要になってくる事業所があると思います。当事務所では、法律改正に伴う就業規則の変更や時間外協定の作成を承ります。今から、長時間労働をしない職場にするためにはどうすればいいのか、この法律改正をきっかけに一緒に考えていきましょう。
お気軽にお問い合わせください。